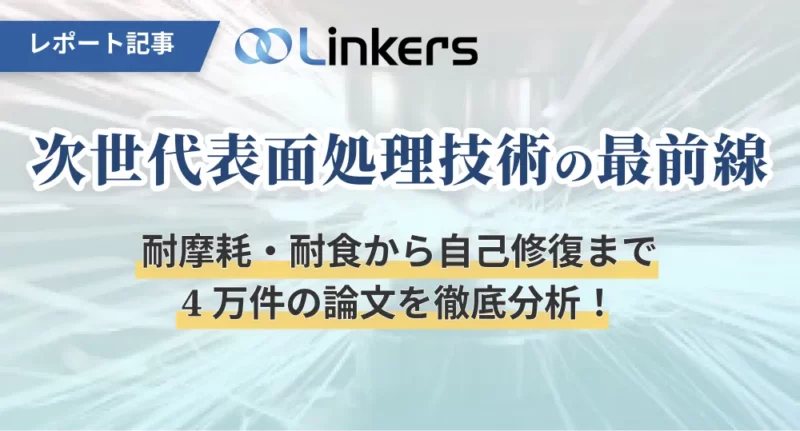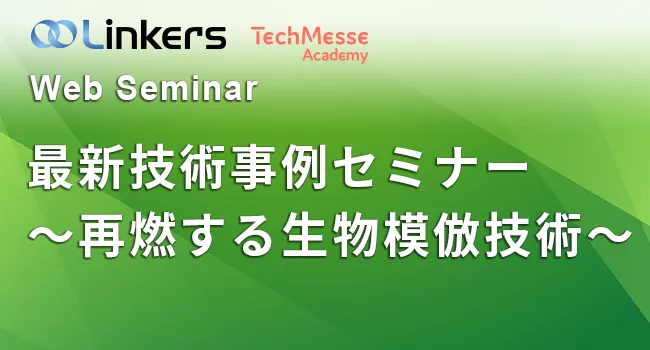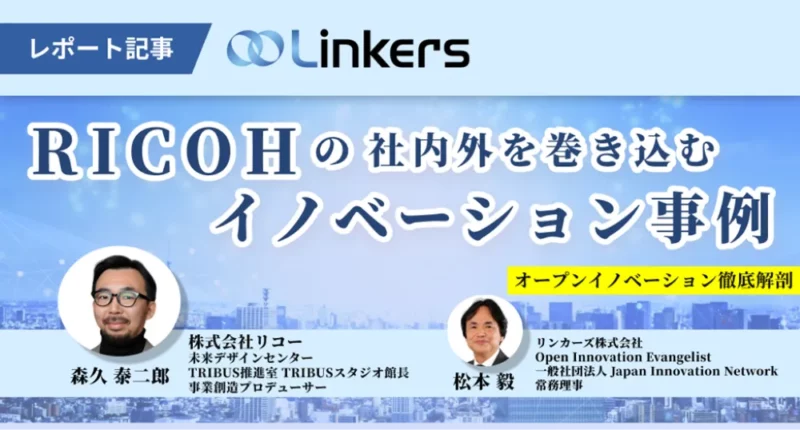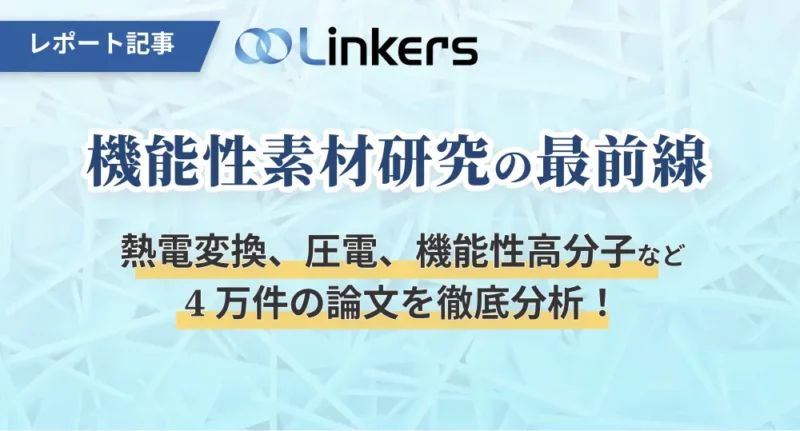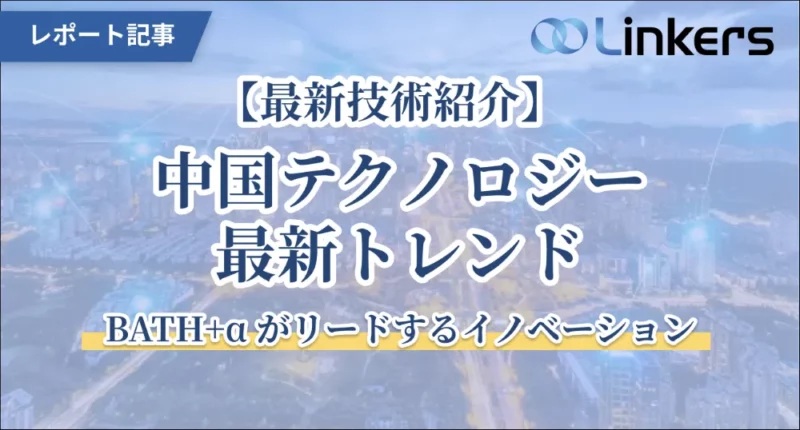- 配信日:2022.08.16
- 更新日:2024.08.07
オープンイノベーション Open with Linkers
マーケティングによる企業改革と価値創造
この記事は、リンカーズ株式会社が主催した「~ 横河電機から学ぶ ~ オープンイノベーション徹底解剖」のお話を編集したものです。
ウェビナーでは、横河電機株式会社の常務執行役であり、マーケティング本部 本部長 CMO の 阿部 剛士 氏に「 R & D から C & D へ ~ マーケティングによる企業改革と価値創造強化 ~ 」についてお話しいただきました。
事業戦略、企業改革に興味がある方は是非ご一読ください。
◆目次
・ VUCA + ~ 予測不能な外部環境 ~
・ 2 度の戦略的転換を行った横河電機
・ 事業の戦略的転換を支える横河電機の「三種の神器」
・ SDGs に貢献するための新規事業戦略
・ 横河電機の企業変革へのアプローチ
・ 事業戦略を担う横河電機マーケティング本部の機能
・ イノベーションを担う横河電機の R & D ( Research and Development )
・ 研究テーマ数とオープンイノベーションの伸長
・ スピード重視のオープンイノベーションと C & D
・ まとめ ~ 指数関数的な社会の変化への対応が大切 ~
VUCA + ~ 予測不能な外部環境 ~
「 VUCA 」は「 LEADING and THRIVING in a VUCA WORLD 」というように、よく「 WORLD 」とペアで使われることが多い言葉です。
「 VUCA 」は4つの単語の頭文字から成り立っています。
・Volatility (変わりやすく)
・Uncertainty (不確実で)
・Complexity (複雑で)
・Ambiguity (あいまい)
つまり「 A VUCA WORLD 」とは「 DISRUPTION (予測不能)」ということです。
残念ながら「『 A VUCA WORLD 』『 DISRUPTION 』が今世紀のニューノーマルになる」というのが世界的な意見の一致であり、現在の企業の経営者たちは非常に大変な時期に経営をしていることになります。
「 A VUCA WORLD 」の中で「 DX (デジタルトランスフォーメーション)」に対応する必要もあり、これだけでも大変なのですが、さらに新型コロナウイルスがやってきました。
これらを全て足した現在の世界はまさに「 Parfect Storm 」です。この大波を乗り越えるためには、競合他社とも協業しなければならないと、私たち横河電機は認識しています。
2 度の戦略的転換を行った横河電機
このような環境の中で、横河電機はどんな取り組みをしているのかを説明します。
横河電機は 100 年を超える歴史がある企業です。横河電機の長い歴史の中で特筆すべきことは、過去2回の戦略的転換期があり、それを乗り越えていることです。
第1回目の転換期は、「横河・ヒューレッド・パッカード( YHP )」という計測事業に転換したタイミングでした。
第2回目の転換期は 30 ~ 40 年ほど前に立ち上がった、現在の制御事業です。横河電機本体は、時代に合わせて製品のポートフォリオを大きく変えながら今に至っています。
しかし、現在横河電機の売上のうち約7割がハイドロカーボンに依存しています。これが私たちにとっての1つのリスクではないかと考えており、脱・ハイドロカーボンを目指しています。
事業の戦略的転換を支える横河電機の「三種の神器」
事業の戦略的転換期を迎えるにあたり、重要なポイントが 3 つあると考えています。
●「 Moonshot (非常に困難ではあるが成功すれば大きなイノベーションを生む壮大な計画・目標)」を打つ
右肩上がりで成長している間は現在の事業の延長で良いのですが、転換期を迎えたならば Moonshot を打ち、バックキャストして事業計画を作っていかなければなりません。
●世界的課題にチャレンジ
横河電機が次の売上の柱を立てるためには、世界的課題にチャレンジする必要があると考えています。
●スピード
「 A VUCA WORLD 」において重要なのはスピードです。スピードを上げるためには組織も企業文化も変えなければなりません。「 agility (機敏さ)」が重要になってくると考えられます。
横河電機の経営における三種の神器(コアコンピタンス)
横河電機には3つのコアコンピタンスがあります。
1つ目は測ること( Measurement )。
可視化するということ、センシティングテクノロジーです。
2つ目は測った結果をもとに制御すること( Control )。
横河電機は「 Distributed Control System ( DCS :分散制御システム)」というものを持っており、世界で初めて DCS を開発したのは横河電機という歴史もあって、制御も得意としています。
3つ目は測ることで出てくる情報( Information )。
IT というよりも OT (オペレーティングテクノロジー)のセクターでの情報を横河電機のコアコンピタンスと認識しています。
横河電機は「 Measurement 」「 Control 」「 Information 」という「三種の神器」で経営しています。
SDGs に貢献するための新規事業戦略
現在から1つ前の中長期計画を作るにあたり、三種の神器をベースにして完全に SDGs にコミットするしかないと考え始めました。今後、世界の脱・ハイドロカーボンの動きは変わらないだろうという仮説のもとに、私たちは SDGs について勉強し始めたのです。
SDGs を先程の三種の神器で因数分解した結果、当時 17 個のうちの 11 個のタイルに対して横河電機は貢献できるという自信を持ちました。そのため横河電機の1つ前の中長期計画では、 SDGs17th に 100% アラインする事業戦略になっています。
横河電機の企業変革へのアプローチ
横河電機は今まさに企業大改革を行っている最中です。私たちはマッキンゼーのフレームワーク「 7S 」を参考にしています。
7S は3つのハード S と4つのソフト S から成り立っています。
- ハード S
- ・Strategy(戦略)
- ・Structure(組織構造)
- ・System(システム)
- ソフト S
- ・Shared value (共通の価値観)
- ・Style(経営スタイル)
- ・Staff(人材)
- ・Skill(能力)
ハードの 3S のうち、私の部署であるマーケティング本部は「 Strategy (戦略)」を担っています。「 Structure (組織構造)」は人材部門、「 System (システム)」は IT 部門の担当です。
現在、マーケティング本部と人材本部、情報システム本部(横河電機ではデジタルソリューション本部と呼称)の3つの部門が会社を変えるために歯車を回しています。