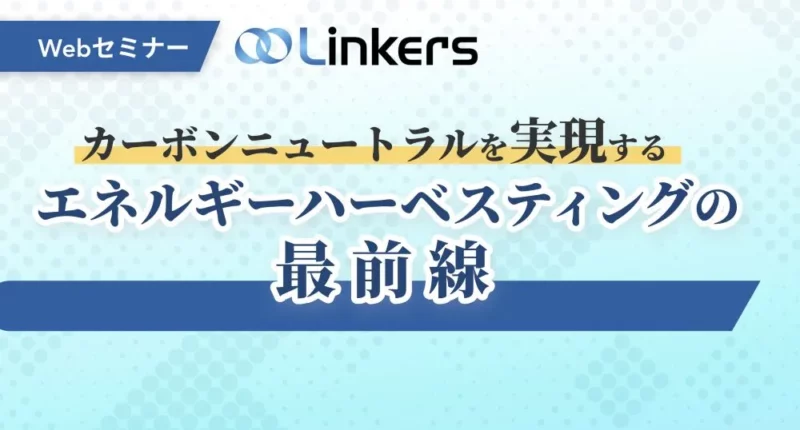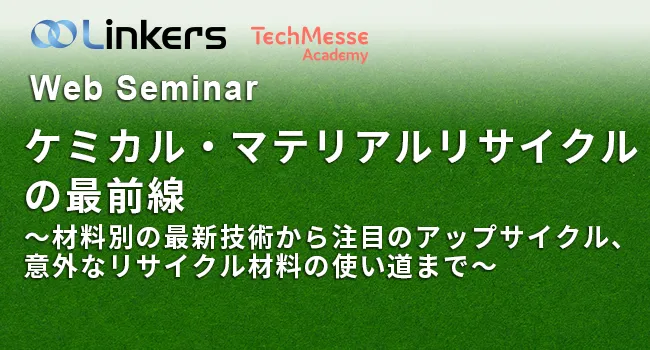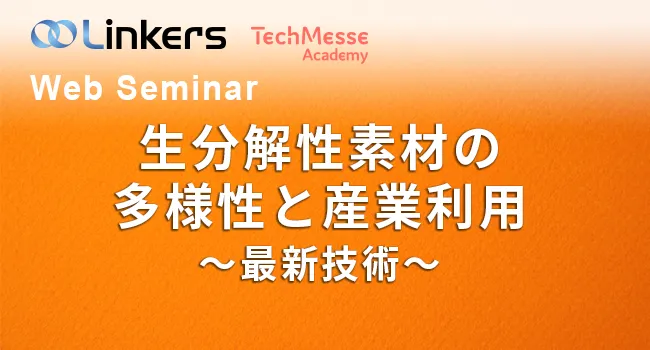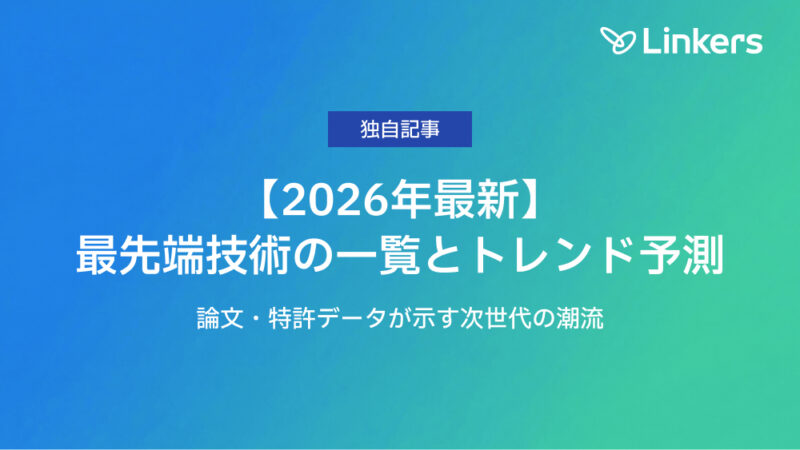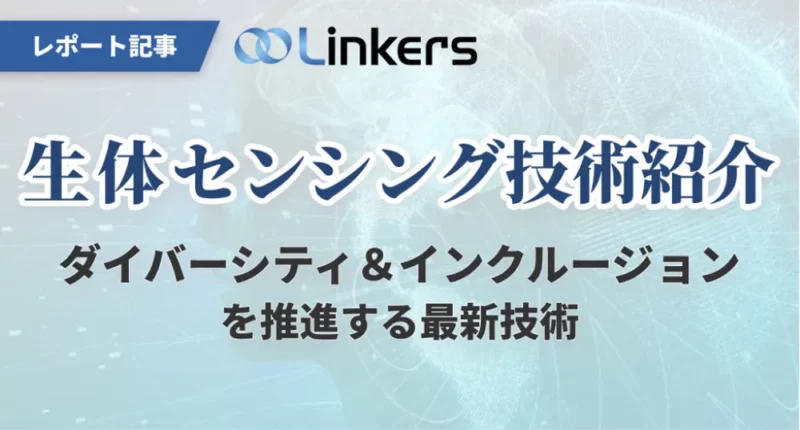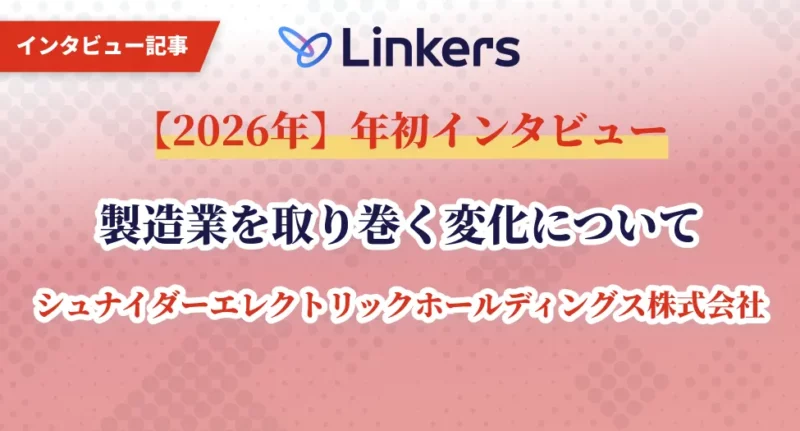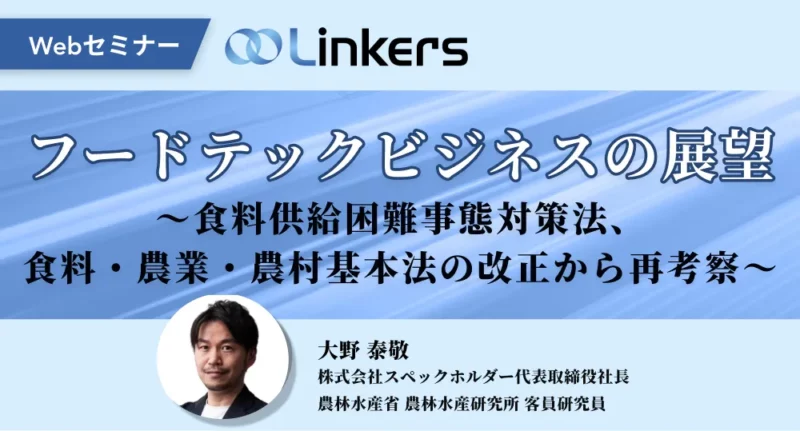
- 配信日:2024.10.31
- 更新日:2025.06.30
オープンイノベーション Open with Linkers
フードテックビジネスの展望~食料供給困難事態対策法、食料・農業・農村基本法の改正から再考察~
食料供給困難事態対策法とは。食料・農業・農村基本法の改正とは
「食料供給困難事態対策法」が施行され、同時に「食料・農業・農村基本法」の改正が行われました。これらの法整備は、日本の食料安全保障を強化し、食料供給の安定性を確保するための重要な一歩となっています。世界的な食料需給の不安定や気候変動による農業への影響が深刻化する中、これらの法律は新たな技術革新とビジネスモデルの導入を促進し、フードテック分野に大きな可能性をもたらしています。
食料供給困難事態対策法とは
食料供給困難事態対策法は、近年の世界的な食料需給のひっ迫や、地政学的リスクの高まりを背景に、日本の食料安全保障を強化するために 2024 年に公布された法律です。この法律は、食料供給に困難が生じる事態に備え、政府が総合的かつ迅速に対応できる枠組みを整備することを目的としています。この法律の重要性は、食料供給のリスクが高まる現代において、国民の生命と健康を守るための基盤を強化する点にあります。また、食料供給の課題に対応するために、新たな技術やビジネスモデルの導入が求められており、フードテック分野への期待が高まっています。これにより、食料生産・流通・消費の各段階での革新が促進され、持続可能な食料システムの構築が進むことが期待されています。
食料・農業・農村基本法の改正とは
食料・農業・農村基本法は、1999 年に制定された日本の基本法であり、食料の安定供給、農業の持続的な発展、そして農村の振興を目的としています。この法律は、食料・農業・農村に関する基本的な施策の方向性を示し、日本の農業政策の基盤となっています。2024 年には、この基本法の改正が行われ、気候変動や国際情勢の変化に対応するための新たな施策が追加されました。特に、スマート農業やフードテックなどの先端技術の導入、農業分野でのデジタルトランスフォーメーションの推進などが強調されています。この改正により、日本の食料・農業・農村政策は新たな段階に入り、持続可能で革新的な農業ビジネスの展開が期待されています。
そこで私どもリンカーズ株式会社は、食料供給困難事態対策法および食料・農業・農村基本法の改正に際し、フードテックやスマート農業領域における、企業の新たなビジネスチャンスを探るべく、Web セミナー『スマート農業/畜産の成功事例~食料供給困難事態対策法、基本法の改正から見直して考える』を開催いたしました。
食料安全保障問題におけるフードテックビジネスのチャンスと、日本国内外の企業の取り組みについて、農林水産省 農林水産研究所 客員研究員で、株式会社スペックホルダー 代表取締役社長の大野泰敬(おおの やすのり)様にご講演いただいた内容を本記事にてご紹介いたします。
大野様が使用された講演資料も、本記事の最後にて無料でダウンロードいただけます。本記事と併せて、ぜひご活用ください。
また、同セミナーでは弊社より、直近 10 年間の農業 ×AI や農業 ×IoT に関連する論文分析に基づき、スマート農業の注目技術と、農業における AI や IoT の具体的な活用事例について解説いたしました。(その詳細は『スマート農業の注目技術~スマート農業技術活用促進法で見直したい「農業×AI/IoT」~』の記事にてご覧いただけます。)
◆目次
● 食料供給困難事態対策法とは。食料・農業・農村基本法の改正とは
● 食料安全保障問題
● 日本における法律の変化(食料・農業・農村基本法、食料供給困難事態対策法)、スマート農業について
● 海外のフードテック動向
●フードテック事例:シンガポールの取り組み
● フードテック事例:Google の取り組み
・Mineral by Google
・Project Tidal
● フードテック事例:マイクロソフトの取り組み
・Project FarmVibes
● フードテック事例:ビルゲイツ氏の取り組み
● フードテック事例:アリババの取り組み
● フードテック事例:中国 IT 系企業の動き
● フードテック事例:日本国内の企業の取り組み
● フードテックの課題:日本企業は世界の企業に勝てないのか
● フードテックの展望:世界は日本に何を求めているのか
食料安全保障問題

日本の食料自給率は 38 % と公表されていますが、飼料自給率を加味すると少し数字は異なってきます。
例えば日本の卵の自給率は 97 % とされていますが、 13 % とかなり低下します。
牛肉の自給率も 47 % から 13 % 、豚肉は 49 % から 6 % 、鶏肉は 64 % から9% に低下します。つまり日本は海外からの輸入にかなり依存しているのが現状です。
また餌代が養殖コストに占める割合も 70 % になっており、そのうち魚粉の国際価格は3倍になっています。
さらに酪農家の 85 % がコスト上昇により経営が悪化しているデータも出てきており、毎月 100 万円以上の赤字が出ている酪農家が急増しています。そして酪農家の6軒に1軒くらいが1億円以上の借金を抱えており、このような酪農家や企業が倒産すると、その地域に与える影響も非常に大きくなると予想されています。
このような話をすると数字が正しいかどうかの議論になりがちです。しかし数字の正確性よりも重要なのは、私たちは海外に依存する生活をしているという事実です。このようなデータを知ったうえで判断を下すことが大切だと考えています。
日本における法律の変化(食料・農業・農村基本法、食料供給困難事態対策法)、スマート農業について
日本もかなり大きな動きを見せている状況です。まず、食料・農業・農村基本法を改定したことが挙げられます。

食料・農業・農村基本法で次の項目が改定されました。
- 1. 食料安全保障の強化
- 2. 農産物や農業資材の安定的な輸入
- 3. 農業法人の経営基盤の強化
- 4. スマート技術の活用
- 5. 収穫量の多い品種の導入促進
- 6. 輸出の促進と備蓄の強化
- 7. 農産物の適正な価格形成
これはこれとして必要な取り組みだと認識しています。

これだけではなく、新しい法案が可決されました。それがこれからのビジネス、特に食の一次産業やそのサポートをしている方々にとって大きな影響を及ぼすと思われます。それが 2024 年6月に可決された「食料供給困難事態対策法」です。

簡単に説明すると、まず農家や食品販売事業者など、特定食料の生産・出荷・販売に関わる全ての人たちに生産計画を提出することが義務化されます。いつ、どこで、誰が、何を作っているのかを国に報告する義務が発生するということです。

そして食料供給が難しくなる事態が発生し、特定食料の供給が2割以上減少する場合、国が計画を変更指示できるようになります。

さらに計画や農地の面積、倉庫の状況などの書類と実態の差を調査することも義務化されます。

上記の義務に従わない場合、罰則の対象となります。このように法案が大きく変わりました。

ここまでに紹介した4つのポイントに加えて、食料供給が困難になり国民が最低限度必要とする食料が不足する場合、配給制度が実施されます。
この法案について良し悪しはありますが、ポジティブな要素として、これから各酪農家が農業のスマート化を進めて作業を効率化していく、そのきっかけになるという点が挙げられます。特にスマート農業やスマート畜産などのサービスを提供する側はあまり儲からないという課題が今までありました。

上の画像は農林水産省が発表した資料から引用したものです。食料供給が大幅に不足する場合、1人あたりの1日の摂取カロリーが 1,900 kcal を下回る、または流通量が2割以上減少した場合は内閣総理大臣を本部長として対策本部が設置され、そこがさまざまな指示を出します。これにより今までスマート化が進められなかった酪農家がこの指示にいきなり従えるかと言ったら難しいでしょう。そのため、緊急事態への対策に協力してくれる企業などに対して国が財政上の措置を行うということを約束しています。おそらく補正予算などが組み込まれ、スマート農業をサポートするようなビジネスに追い風になる可能性が高まっていると予想できます。

どういう品目が対象になるのかというと、米、小麦、畜産など私たちが生きていくうえで必要なものが対象になります。魚は入っていないのですが、例えば養殖の場合はすでに提出が義務化されています。この辺りのことを踏まえると、今後1年間で市場が大きく動く可能性があるため、ビジネスチャンスも広がるのではないかと予想しています。
様々なデータがありますが、 中には2030 年ごろまでには 3000 万人分の食料しか提供できなくなるのではないかという警鐘を鳴らす人が出るくらい、現状のままコストの高騰が続くと危機的な状況に陥る可能性が危惧されています。
また農業も養殖も畜産も必要なエネルギーがとても多く、例えば牛舎に設置する大型の扇風機を数百台動かすために大量の電力が必要になります。すると農家にかかる月々の電気代は 20 〜 30 万円は当たり前で、多いところだと 50 万円程度かかることもあります。このような形でさまざまなコストがかかることで経営を圧迫し、食の生産者が倒産してしまう状態にかなり近づいて来ている状況です。その対策として国は法案を作り、民間企業は新しいサービスを提供することが求められるでしょう。