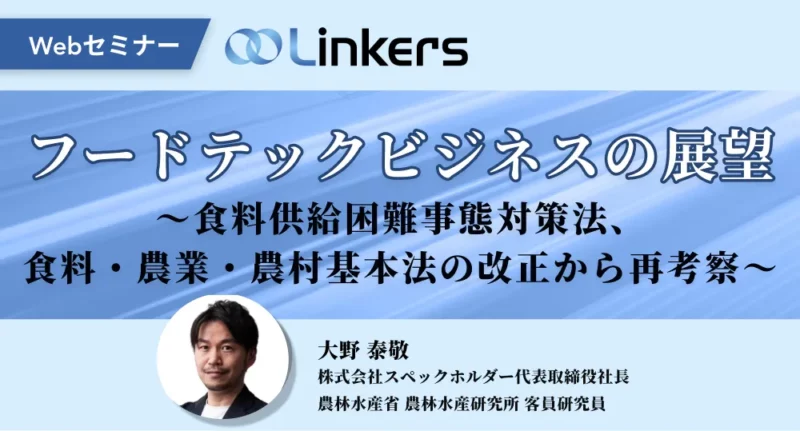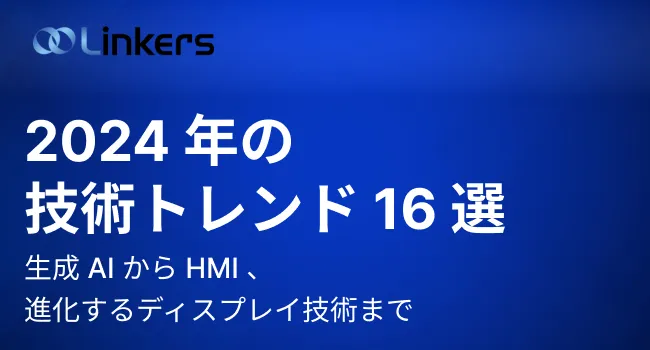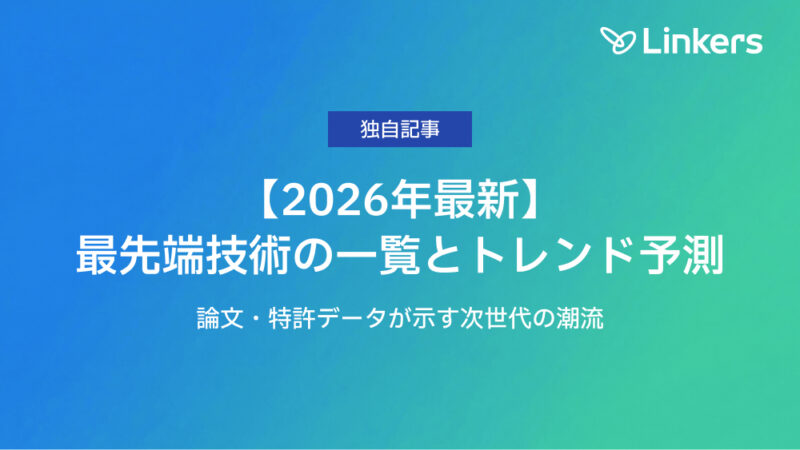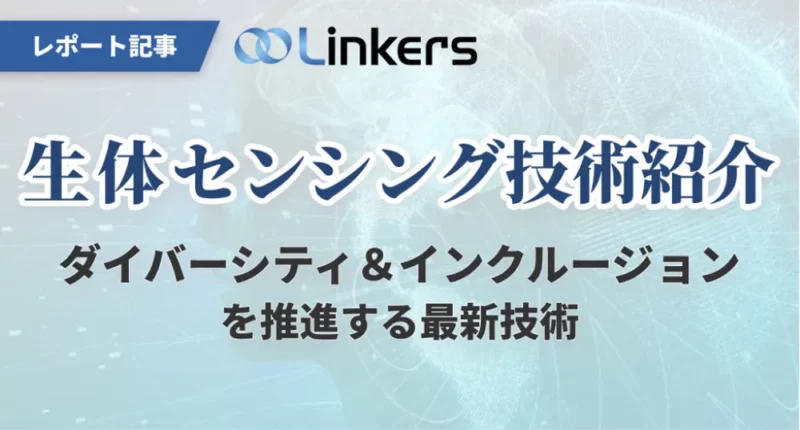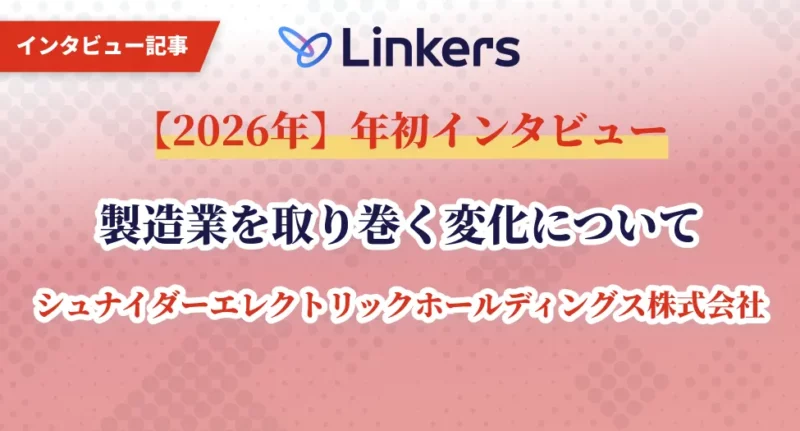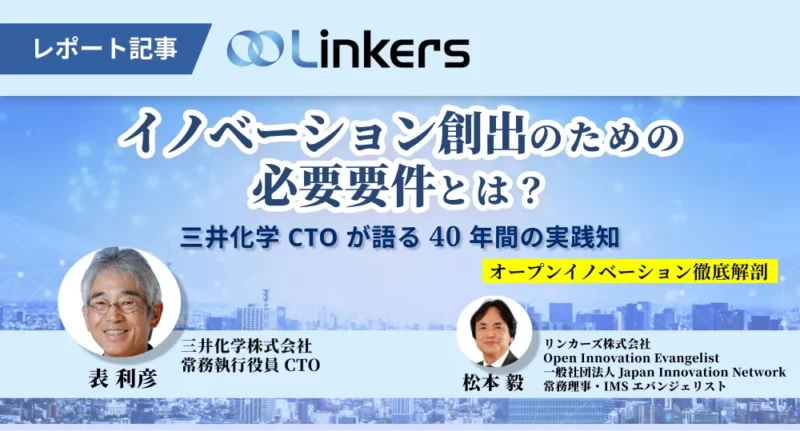
- 配信日:2025.10.10
- 更新日:2025.12.25
オープンイノベーション Open with Linkers
三井化学CTOが語る、40年の知見を凝縮したイノベーション戦略と新事業開発の極意
この記事は、リンカーズ株式会社が主催したWebセミナー『イノベーション創出のための必要要件とは?三井化学 CTO が語る 40 年間の実践知』のお話を編集したものです。
三井化学株式会社 常務執行役員 CTO の表 利彦(おもて としひこ)様が、 40 年にわたる豊富な実践経験から得たイノベーション創出の知見を詳細に解説。経営戦略に基づく新事業創造の論理フロー、ニッチ戦略の重要性、新事業開発センターの仕組み作りから、 CVC ファンドや細胞培養事業などの具体的な成功事例まで、技術を収益性のあるビジネスに変える実践的なアプローチを紹介しています。
目次
●経営戦略に基づく新事業創造(イノベーション)
・イノベーションを成功に導く経営戦略の論理フロー
・三井化学のイノベーション戦略:『VISION 2030』が描く未来
・三井化学の事業二分化戦略:イノベーションを加速する組織再編
・三井化学が実践する「ニッチ戦略」:イノベーションで市場の「生態的地位」を確立
●三井化学における新事業開発(イノベーション)の仕組みづくり
・三井化学「新事業開発センター」の設立経緯とイノベーション推進体制
・新事業開発センターが担う「事業デザイン」:イノベーション創出とスタートアップ連携
●新事業を開発するための組織運営の考え方
●三井化学のイノベーション実践事例:CVCファンドと細胞培養事業
・三井化学のオープンイノベーション:CVCファンド『321Force』と『321Catalysts』によるスタートアップ投資
・細胞培養事業『InnoCell』:三井化学が挑むバイオ医薬品分野のイノベーション
経営戦略に基づく新事業創造(イノベーション)

まず経営戦略に基づいて、いかに新事業を創造するかについて説明します。
イノベーションを成功に導く経営戦略の論理フロー
経営は上位概念からの論理フローがなければ上手くいかないと考えています。そのため各社に、最上位の概念として将来実現したい姿(経営ビジョン)があるはずです。
経営ビジョンの下に、経営理念があります。これは永続的に成長するための考え方です。経営ビジョンと経営理念が矛盾しないこと。そしてこれらを全社員がきちんと理解することが経営において重要だと思います。
経営理念の下にあるのが経営戦略で、ある程度の期間内での経営の戦略方向性を意味します。三井化学の場合、 2022 年を元年として 2030 年までの長期経営戦略を作り、推進しています。
経営戦略の下にあるのが、戦略を具体的にどういう方法論で進めていくのかを示す経営戦術です。経営戦術が明確でないと、どういうものを用意して、どう経営に役立てていくかが見えてきません。
経営戦術が明確になると、その戦術のためにどのような資産や技術を使うのかという経営戦技が見えてきます。
このような論理のフローを理解しないままに、例えば研究開発部門が自分たちの戦略だけを一人歩きさせてしまうと、経営資源のロスが出てしまいがちです。まして、オープンイノベーションを行うならば、社外の人たちとの共通の価値観を持たないと成功確率は上がりません。
一番最後に出てくるのが経営戦意。すなわち人財や組織、モチベーションなどです。個人的に、会社という組織において人財は非常に重要な資産である為、人財を育成していくことが求められます。そして人財の育成・成長には、各人のモチベーションが欠かせません。しかし、モチベーションアップのための局所的なイベントをやったところで、本当の意味で人財のモチベーションは上がらないでしょう。人財を育成することは、会社が成長し、社会に価値を提供し続けるための手段。そして、生み出した利益を次世代に再投資したり、ステークホルダーに還元したりして、さらなる会社の成長、つまり会社を構成する人財の成長につなげる。このようなフローがないと、長期的な人財の育成、そのためのモチベーション向上は生まれないというのが私の考えです。
また、論理のフローを作り、それを全社的な指針として社内で共有すると、社員から意見が出てきやすくなります。経営ビジョンや経営理念を実現するために動くのは社員たちです。社員から積極的に意見が出る組織を作るためにも、論理のフロー作りとその理解が重要になります。
三井化学のイノベーション戦略:『VISION 2030』が描く未来

具体例として、三井化学の長期戦略『 VISION 2030 』について少し説明します。今までアナログで行っていた業務に可能な限りデジタルを移植し、生産性を上げる。その考えをベースに、サーキュラーエコノミー型のビジネスモデルを初期の段階から考えるというのが『 VISION 2030 』の一部です。
サーキュラーエコノミー型のビジネスモデルを構築していくと同時に、素材を扱う会社として、お客様の困りごとを解決する素材をベースにその課題解決のソリューション型の新しい事業を作っていくことが、今後の課題となっています。
三井化学の事業二分化戦略:イノベーションを加速する組織再編
『 VISION 2030 』とは別に、 経営概況説明会にて、三井化学の社長・橋本が大きな発表を行いました。その内容は、祖業である石油から基礎化学品を作る事業本部(ベーシック & グリーン・マテリアルズ)を今までと異なる枠組みで経営することを考えていくというものです。
この実現には、様々なグリーンケミカル、新しいテクノロジーの導入が欠かせません。そのための投資や開発を三井化学が単独で行うのは限界があります。そこで国の支援を受けながら、他社の協力も得て進めていこうと考えています。
ただ、『 VISION 2030 』で掲げる成長3領域のICT、モビリティー、そしてライフ&ヘルスと、ベーシック & グリーン・マテリアルズとでは、経営戦略も投資概念も、期待される収益率も全く別物です。この2つの取り組みを1つの組織として進めていくのは難しいだろうということで、2つの組織に分け、それぞれ経営していく形を構想しています。この変化は、イノベーションチームや研究開発チームが今までにない手法・体制を採用するチャンスになり得ると個人的に考えています。
三井化学が実践する「ニッチ戦略」:イノベーションで市場の「生態的地位」を確立

事業ごとに組織を大きく2つに分けた後、特に成長3領域に関してどのように経営を進めていくのかを説明します。キーワードは「ニッチ」です。ここで言うニッチとは、一般的に使われる「隙間・溝」といった意味ではなく、「エコシステムの生態的地位」という意味です。1つの生態系の中でどこかが欠けると、その生態系が歪んで維持できなくなります。三井化学は生態系を維持するうえで、様々なステークホルダーの方々から「三井化学がここにいてほしい」と言ってもらえるような重要なポジションを長期にわたって確保していく。つまり「ニッチな状態」を作ることが成長する機会になると考えています。
この状態を維持するには、戦略に応じてやるべきこと、進め方が異なりますが、1つ例を紹介します。
今まで三井化学では触媒化学を使ってユニークな材料を作り、それをポリマー化し、さらに特異的なポリマーを作成。それから、エラストマー(ゴムのような弾性を持つ高分子材料)などと組み合わせながらコンパウンド化(複合材料化)し、それをいろんな産業でお使いいただく。また、そのようにして開発した素材の一部を加工しながら、完成度を上げていく。このように材料単体で非常に強い技術を持っていました。
このような、技術価値が上がるにつれて顧客価値も上がる無限規格品はかつて、技術を高めていけばどんどん売れました。しかし最近は、様々な国が無限規格品に巨額の投資を行い、シェアを拡大している状況です。単体技術だけで無限規格品を開発し続けても、資本力や研究人員の多い国には勝てません。ではどうすれば勝てるか。その可能性として単一の技術ではなく複数の技術を使い、材料のみならず高度な加工技術を組み合わせて複雑性を高めることがあると考えています。
一方、技術価値が上がっても、お客様にとっての価値が上がらなくなると、それ以上はオーバースペックです。この状態になると、価格競争やキャパ競争が起こります。このような競争は、日本企業にとってあまり得意ではないことだと思っていますし、技術力の高さで生き残ろうとしている企業にとって面白い領域でもないでしょう。
もし顧客価値が上がらなくなったら、そのバリューチェーン上で複数回の価値提供が行えるようにすることが重要になると考えています。また、デジタルを活用したサービスと材料を組み合わせて何ができるかを思考することも有効な手段だと考えています。
【 PR 】
貴社の技術課題に最適なパートナーを迅速に探索し、イノベーションを加速。
Linkers Sourcing サービスについてはこちら
三井化学における新事業開発(イノベーション)の仕組みづくり

市場や顧客の困りごとを解決するソリューションを生み出し、提供するためのイノベーションを興そうとしても、そう簡単にはいかないものです。
イノベーションの成功率を上げるには、そのための体制や仕組みづくりが必要になります。ここからは、イノベーションを興すにはどのような体制・仕組みづくりが必要か、三井化学での私の取り組みを例にお伝えします。
三井化学「新事業開発センター」の設立経緯とイノベーション推進体制

ここ3年ほど、私は三井化学の中で新事業開発センターを担当しています。その中で、新しい事業を作る大まかな仕組みをメンバーと共に試行錯誤しながら作ってきました。
社内の様々な部門からビジネスのアイデアが出てきますが、市場から離れた部門のアイデアは本当にニーズがあるのかわからず、不確実性が高いです。その場合に重要なのは、市場に出て新鮮なニーズを獲得していくことなのですが、例えば研究開発を行っているようなメンバーに「市場の意見を取ってきてください」と言っても、彼らは市場から離れたポジションで研究開発を専門にやっているわけですから、すぐにはできません。私も研究開発を担当していた頃は、自分で市場の意見を集めることができず、営業やマーケティングのメンバーとともにお客様のところへ行くことで、意見を集める習慣や方法を身につけてきました。これを、新事業開発センターで仕組み化しようと考え、進めているのです。
また、新事業開発センターは社内のアイデアを実現する際、社外の人たちと協業する必要があればその橋渡しをし、例えば協業相手がスタートアップならば CVC (コーポレート・ベンチャーキャピタル)を作るといったサポートなども行っています。
新規事業を立ち上げるまでの主な流れとして、まずはビジネスアイデアを持っている人たちに、社内の様々なコミッティーに対してピッチを行ってもらいます。その結果から、ビジネスプランを実現するために新事業開発センターのメンバーが並走できるかどうかを判断する。その判断ができたら、アイデアを持っている人と、新事業開発センターのメンバーが市場の意見を集め、開発をする。あるいは社外の人々と協業する。これを何回も繰り返して確度を高めていきます。
【 PR 】
新技術・製品の市場開拓を支援。貴社のビジネスを成功に導きます。
Linkers Marketing サービスについてはこちら

新事業を開発するための組織運営の考え方
新事業開発センターの役割は「事業デザイン」です。事業デザインにおいて最も重要なのは、社会・市場・顧客の困りごとを解決するためにどのような価値提供ができるか考えること。そして価値提供の実現には、自社で持っているアセット、新しく出てきている技術、社外にあるアセットなどを組み合わせ、仮説を立てながらどんどん軌道修正し、より現実的な方向のビジネスに持っていくことが大切になります。三井化学において、これを担っているのが新事業開発センターです。
新事業開発センターは将来の社会課題を予想し、いち早くソリューションを提供するためのビジネスを創り出していくことが求められます。そのためには市場の変化、お客様のニーズの変化を素早く調査する必要があるものの、自社だけで十分に行えるとは限りません。そこで重要になってくるのが、世界中のスタートアップと協力関係を作ることだと、個人的に考えています。新しい市場に挑戦しているスタートアップには、鮮度の高い情報が集まりやすいです。そのようなスタートアップを窓口としてマーケティングを行った方が、自社で行うよりも効率が良い場合もあるでしょう。
そこで三井化学では、様々なスタートアップに出資しながら、自社の学びを得てビジネスを試行錯誤しやすくする。このような双方にメリットのある関係を構築しようと考えています。